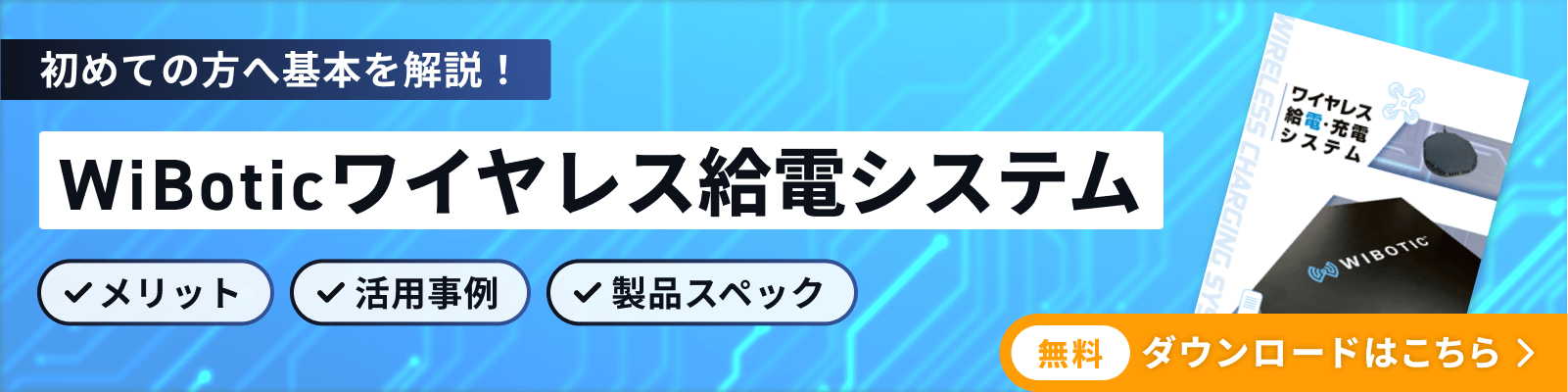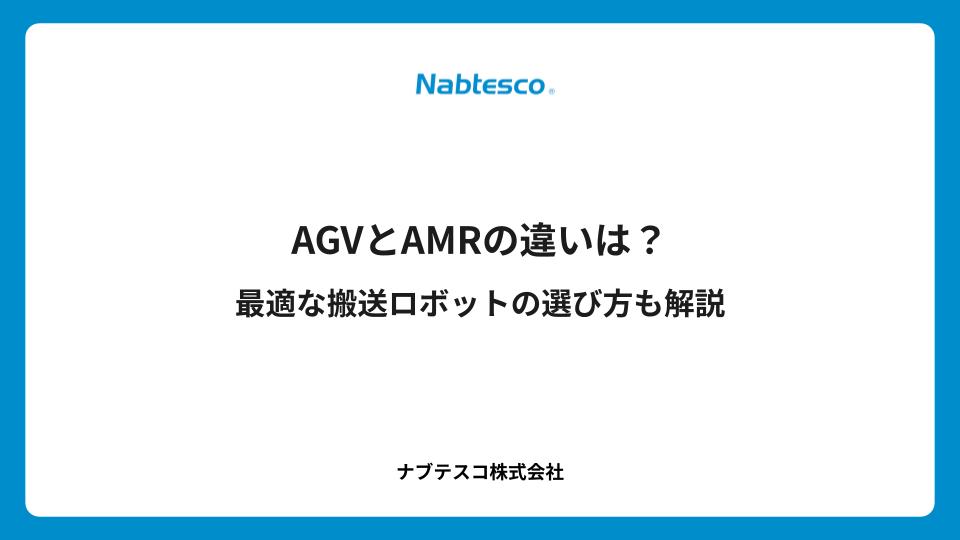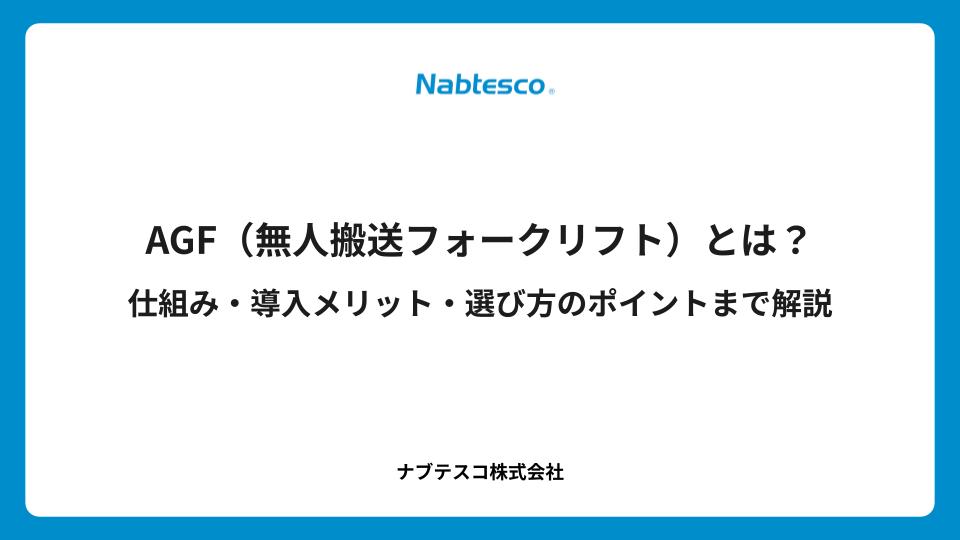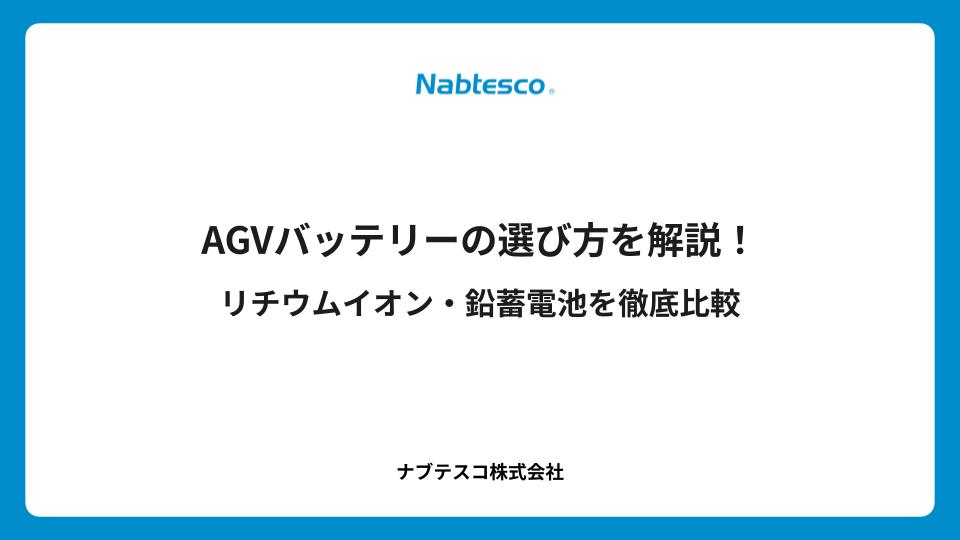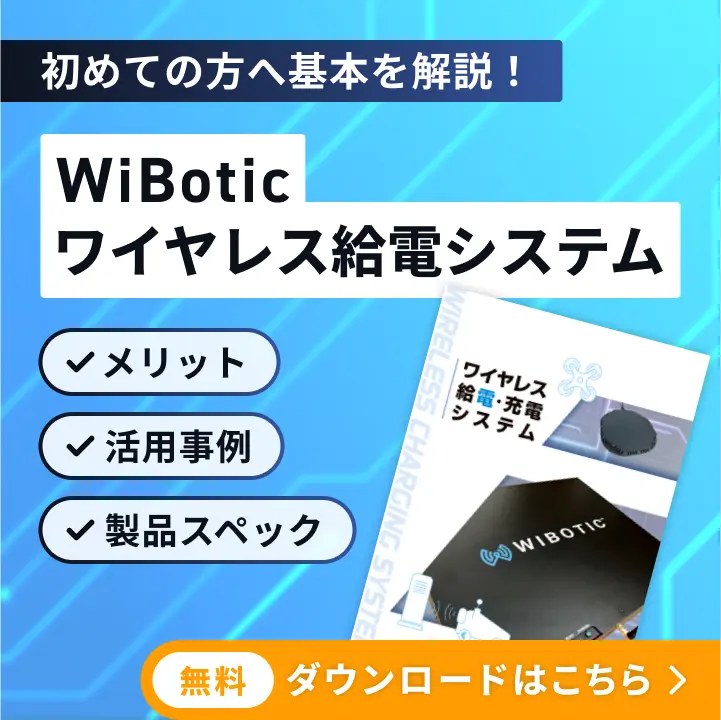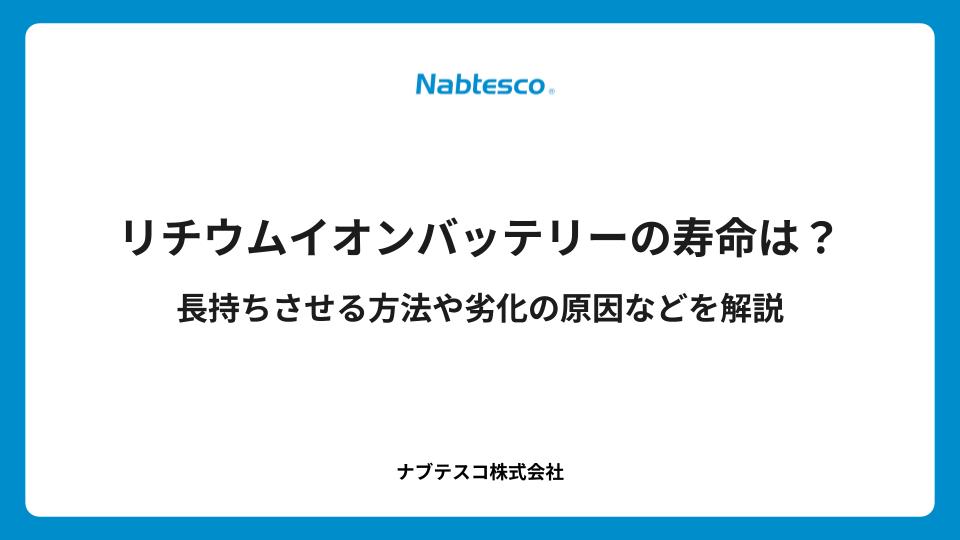
これらの設備の心臓部ともいえるリチウムイオンバッテリーですが、「どのくらいの期間使用できるのか」「劣化を防ぐにはどうすればよいのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、リチウムイオンバッテリーの基本的な寿命から、劣化の原因、長持ちさせる具体的な方法まで解説します。
リチウムイオンバッテリーとは?基本的な特徴と用途
リチウムイオンバッテリーは、その高いエネルギー密度と長寿命という特徴から、現代社会の多岐にわたる分野で不可欠な存在となっています。スマートフォンやノートパソコンといった身近な電子機器から、電気自動車(EV)、さらには産業用の大型機器に至るまで、幅広い用途で活用されています。
リチウムイオンバッテリーの構造と動作原理
リチウムイオンバッテリーは、主に「正極」「負極」「電解液」「セパレーター」の4つの主要な構成要素から成り立っています。
正極:リチウム金属酸化物(例:コバルト酸リチウム、リン酸鉄リチウムなど)が用いられ、リチウムイオンを放出・吸蔵します。
負極:主にグラファイトなどの炭素材料が用いられ、リチウムイオンを吸蔵・放出します。
電解液:リチウム塩を有機溶媒に溶かしたもので、正極と負極の間でリチウムイオンを移動させる媒体となります。
セパレーター:正極と負極が直接接触するのを防ぎつつ、リチウムイオンのみを通過させる微細な孔を持つ膜です。
また、動作原理は、リチウムイオンが正極と負極の間を行き来することで電気エネルギーを蓄えたり放出したりする点にあります。
充電時:外部から電力が供給されると、正極からリチウムイオンが電解液を通って負極へ移動し、負極に蓄えられます。同時に、電子は外部回路を通って負極へ移動します。
放電時:負極に蓄えられたリチウムイオンが電解液を通って正極へ移動します。この際、電子は外部回路を通って正極へ移動し、この電子の流れが電流として取り出され、機器の動力源となります。
企業での主な用途(AGV・AMR・産業機器など)
リチウムイオンバッテリーは、その高出力、長寿命、そしてメンテナンスの容易さから、企業における様々な用途で導入が進んでいます。
AGV(無人搬送車)・AMR(自律走行搬送ロボット
工場や倉庫内での資材運搬、製品の自動搬送に不可欠です。高頻度な充放電に耐え、長時間の稼働を可能にするリチウムイオンバッテリーは、生産性向上に貢献します。
産業機器
電動フォークリフト、高所作業車、電動工具、建設機械、清掃ロボットなど、幅広い産業用機器の動力源として採用されています。従来の鉛蓄電池と比較して、小型・軽量でありながら高出力を維持できる点がメリットです。
定置用蓄電池システム(ESS)
再生可能エネルギーの貯蔵や、ピークカット・ピークシフトによる電力コスト削減のために、工場や商業施設で導入されています。
電気自動車(EV)
乗用車だけでなく、商用バンやバス、トラックなどの電動化にもリチウムイオンバッテリーが広く用いられ、輸送分野の脱炭素化を推進しています。
医療機器
ポータブル医療機器や非常用電源など、高い信頼性と安定性が求められる分野でも利用されています。
これらの用途において、リチウムイオンバッテリーは単なる電源としてだけでなく、運用効率の向上、コスト削減、そして環境負荷低減といった多角的なメリットをもたらしています。
リチウムイオンバッテリーの寿命はどのくらい?
リチウムイオンバッテリーの寿命は、その使用状況や保管環境によって大きく変動しますが、いくつかの主要な指標から目安を把握することができます。主に「充放電サイクル数」と「カレンダー寿命(経年劣化)」という二つの側面から寿命を考えるのが一般的です。
充放電サイクル数による寿命の目安
リチウムイオンバッテリーの寿命を測る上で最も重要な指標の一つが、充放電サイクル数です。ここでいう「1サイクル」とは、バッテリー容量の100%分を放電し、再び100%まで充電する一連のプロセスを指します。例えば、50%放電して充電を繰り返した場合、それが2回で1サイクルとカウントされます。
一般的に、リチウムイオンバッテリーは500サイクルから1,000サイクル程度の充放電を繰り返すと、初期容量の約80%まで性能が低下すると言われています。この80%という数値は、多くのメーカーがバッテリーの「寿命」とみなす一つの目安です。産業用機器やAGV(無人搬送車)、AMR(自律移動ロボット)など、頻繁な充放電を繰り返す用途では、このサイクル寿命がバッテリー交換時期を決定する重要な要素となります。
カレンダー寿命(経年劣化)について
リチウムイオンバッテリーは、充放電の有無にかかわらず、時間とともに自然に劣化が進行します。これをカレンダー寿命、または経年劣化と呼びます。
バッテリー内部の電解液の分解や電極材料の構造変化などが、時間経過とともに不可逆的に進行し、結果として容量が減少したり、内部抵抗が増加したりします。
この経年劣化は、特に高温環境下での保管や満充電状態での長期保管によって加速される傾向があります。たとえ使用頻度が低くても、製造されてからの期間が長くなると、バッテリーの性能は徐々に低下していきます。
容量維持率と実用寿命の関係
バッテリーの「容量維持率」とは、初期のバッテリー容量に対して、現在のバッテリーが保持できる最大容量の割合を示します。例えば、初期容量が100Ahのバッテリーが、現在80Ahまでしか充電できなくなった場合、容量維持率は80%となります。
多くのリチウムイオンバッテリーにおいて、初期容量の80%を下回った時点が「実用寿命」と判断されることが一般的です。
これは、80%を下回ると、稼働時間の著しい短縮や性能の低下が顕著になり、機器の本来の性能を発揮できなくなるためです。特に、AGVやAMRなどの産業用途では、バッテリー容量の低下は稼働率や生産性に直結するため、この80%という基準は運用上非常に重要な目安となります。
リチウムイオンバッテリーの寿命の確認方法は?
リチウムイオンバッテリーの寿命や劣化度合いを確認する方法は、そのバッテリーが搭載されているデバイスや用途によって異なります。一般的に、以下の方法でバッテリーの状態を把握できます。
デバイスのOSやメーカー提供機能を利用する
スマートフォンやノートパソコンなどのコンシューマー向けデバイスでは、OSの機能やメーカーが提供する診断ツールを通じて、バッテリーの健康状態(SOH: State of Health)を確認できることが一般的です。
スマートフォンの場合: iOSデバイスでは「設定」アプリ内の「バッテリー」項目で「バッテリーの状態と充電」から最大容量の割合を確認できます。Androidデバイスでは、メーカーや機種によって異なりますが、設定メニュー内や専用アプリで同様の情報を確認できることがあります。
ノートパソコンの場合: WindowsではコマンドプロンプトやPowerShellでバッテリーレポートを生成したり、メーカー提供の診断ツールを使用したりして、設計容量に対する現在の最大容量などを確認できます。MacBookでは「システム設定」の「バッテリー」項目で「バッテリーの状態」を確認できます。
これらの表示は、新品時のバッテリー容量を100%とした場合の現在の最大容量の割合を示しており、この数値が低下するほどバッテリーの劣化が進んでいることを意味します。
専門機器による測定
より専門的かつ詳細な診断が必要な場合は、バッテリーテスターやインピーダンスアナライザーなどの専門機器を用いて、バッテリーの容量、内部抵抗、電圧特性などを直接測定する方法があります。
特に内部抵抗は、バッテリーの劣化が進むと増加する傾向があるため、重要な指標となります。これらの測定は、バッテリーの専門知識を持つ技術者やサービスプロバイダーによって行われることが一般的です。
体感的な変化から判断する
上記の数値的な確認方法だけでなく、日常の使用における体感的な変化も、バッテリー寿命の重要なサインとなります。
・充電の持ちが明らかに悪くなった
・充電時間が異常に短くなった、または長くなった
・バッテリーが膨張している(物理的な変形)
・使用中に異常な発熱がある
・特定の充電残量で急に電源が落ちる
これらの症状が見られる場合、バッテリーの寿命が近づいているか、何らかの異常が発生している可能性が高いため、早めに確認し、必要に応じて交換を検討することが推奨されます。
リチウムイオンバッテリーが劣化する原因
リチウムイオンバッテリーの寿命を短縮させる主な原因は、バッテリー内部で進行する化学的な変化と、外部からの物理的なストレスにあります。これらの要因が複合的に作用し、バッテリーの容量低下や性能劣化を引き起こします。
主な劣化原因は以下の通りです。
電解液の分解とSEI層の過剰な成長
バッテリーの充放電サイクルが進行したり、特に高温環境に晒されたりすると、電解液が分解し、電極表面に固体電解質界面(SEI層)が形成されます。このSEI層は初期にはバッテリーの安定化に寄与しますが、過剰に成長するとリチウムイオンの移動を妨げ、内部抵抗の増加や容量の低下を招きます。
電極活物質の構造破壊
充放電を繰り返すことで、リチウムイオンが正極と負極の間を出入りする際に、電極活物質の結晶構造に体積変化によるストレスがかかります。これにより、微細なひび割れや構造の破壊が生じ、リチウムイオンを吸蔵・放出できるサイト(場所)が減少し、バッテリーの容量が不可逆的に低下します。
リチウムデポジション(金属リチウム析出)
特に低温環境下での充電や急速充電、あるいは過充電が行われた際に、負極のリチウムイオンが電極活物質に挿入されずに金属リチウムとして表面に析出する現象です。
このリチウムデポジションは、バッテリー容量の低下に直接つながるだけでなく、デンドライト(樹枝状結晶)を形成し、内部短絡や発熱・発火のリスクを高める可能性があります。
不適切な温度管理
リチウムイオンバッテリーは熱に非常に敏感です。高温環境下での使用や保管は、電解液の分解を加速させ、SEI層の過剰な成長、電極活物質の劣化を促進します。逆に極端な低温環境も、リチウムデポジションを誘発するなど、バッテリー性能に悪影響を与えます。
過充電・過放電
バッテリーの推奨電圧範囲を超えて充電する過充電や、極端に低い電圧まで使い切ってしまう過放電は、電極材料に大きなストレスを与え、不可逆的な劣化を引き起こします。過充電は発熱やガス発生を招き、過放電は負極の銅集電体の溶出や電極活物質の構造破壊に繋がり、容量低下や安全性低下を招きます。
急速充電・急速放電
電極への負荷が大きく、リチウムデポジションの発生や電極活物質の劣化を早める傾向があります。特に、大電流での充電・放電はバッテリー内部の発熱を伴いやすく、前述の温度ストレスとも関連して劣化を加速させます。
リチウムイオンバッテリーの寿命を伸ばす方法
適切な充電管理(充電深度・充電タイミング)
リチウムイオンバッテリーの寿命を延ばすには、充電の仕方、特に充電深度と充電タイミングが非常に重要です。バッテリーを100%まで満充電にしたり、0%まで使い切って過放電状態にしたりすることは、バッテリーに大きなストレスを与え、劣化を早める原因となります。理想的な充電範囲は、バッテリー容量の約20%から80%の間で運用することです。
継ぎ足し充電は、リチウムイオンバッテリーにとって有効な充電方法です。バッテリー残量が少なくなったら、完全に使い切る前にこまめに充電することで、バッテリーへの負担を軽減し、寿命を延ばすことができます。
また、急速充電は便利ですが、バッテリーに大きな負荷がかかるため、可能な限り通常の充電速度で充電することをおすすめします。
温度管理の重要性
リチウムイオンバッテリーは、温度に対して非常に敏感です。特に高温環境下での使用や保管は、バッテリー内部の化学反応を促進させ、劣化を大幅に早める最大の要因の一つです。メーカーが指定する動作温度範囲(一般的には10℃~30℃程度)を守ることが、寿命を延ばす上で不可欠です。
低温環境もまた、バッテリー性能に影響を与えます。極端な低温では、バッテリーの内部抵抗が増加し、充電効率が低下するだけでなく、リチウム金属の析出(プレーティング)を引き起こし、安全性や寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。
産業機器やAGV・AMRなどでは、冷却ファンやヒーターといった温度管理システムを適切に導入し、バッテリーが常に最適な温度範囲で動作するよう管理することが重要です。
定期的なメンテナンスとモニタリング
リチウムイオンバッテリーの寿命を最大限に引き出すためには、定期的なメンテナンスと常時モニタリングが不可欠です。多くのリチウムイオンバッテリーパックには、バッテリー管理システム(BMS)が搭載されており、電圧、電流、温度といった重要なパラメーターを監視しています。
BMSによる監視を通じて、過電圧、過電流、過熱、過放電などの異常を早期に検知し、保護機能を動作させることで、バッテリーの損傷を防ぎます。
まとめ
本記事では、リチウムイオンバッテリーの寿命が、充放電サイクル数や経年劣化によって限りがあること、そして適切な充電・温度管理が寿命を延ばすために重要であることを解説しました。特に、AGV(無人搬送車)やAMR(自律移動ロボット)といった産業用途では、バッテリーの劣化が稼働率やコストに直結する大きな課題です。
この課題を解決するためには、バッテリーに負担をかけず、常に最適な状態を保つことが不可欠です。そこで注目されているのが、ワイヤレス給電システムです。
ナブテスコが提供する「Nabtesco WiBoticワイヤレス給電・充電システム」は、この課題に対する最適なソリューションです。ケーブル接続が不要なため、停車中の機会充電(スキマ時間充電)を容易に実現できます。これにより、バッテリーの過充電や過放電を防ぎ、寿命を大幅に延長します。さらに、充電のために稼働を停止する時間が減るため、AGVやAMRの稼働率が向上し、生産性の最大化にも繋がります。
また、WiBoticのシステムはコンパクトかつ軽量で、さまざまなロボットに後付けが可能です。充電可能距離が長く、位置ズレの許容範囲が広いため、屋外や停止精度が低い環境でも安定して充電できます。
リチウムイオンバッテリーの課題を解決し、現場の省人化とコスト削減を実現する「Nabtesco WiBoticワイヤレス給電・充電システム」。より詳細な情報や導入事例については、ぜひナブテスコ株式会社のウェブサイトをご確認ください。
ナブテスコのワイヤレス給電についてはこちら
https://wireless-power.nabtesco.com/