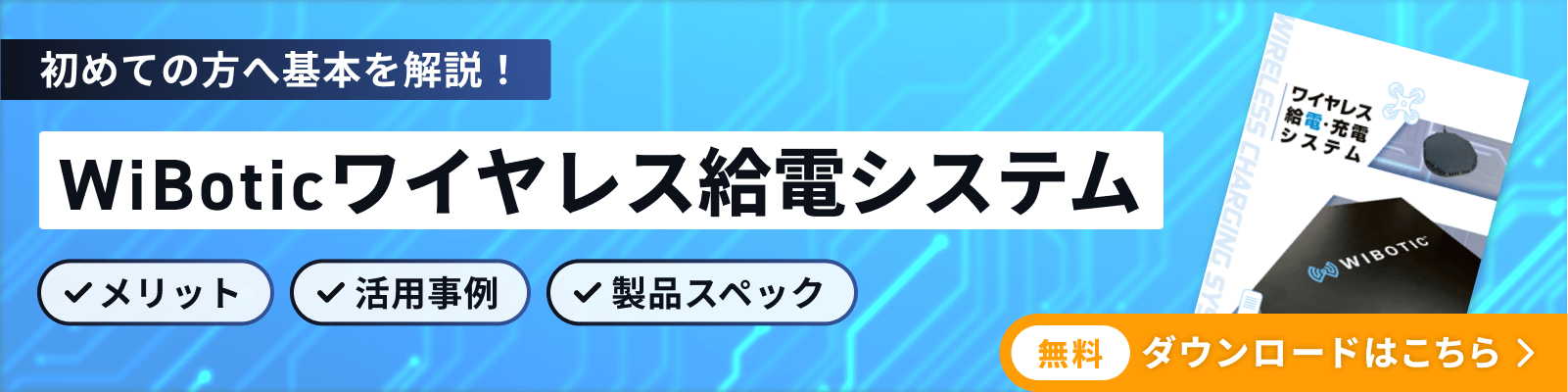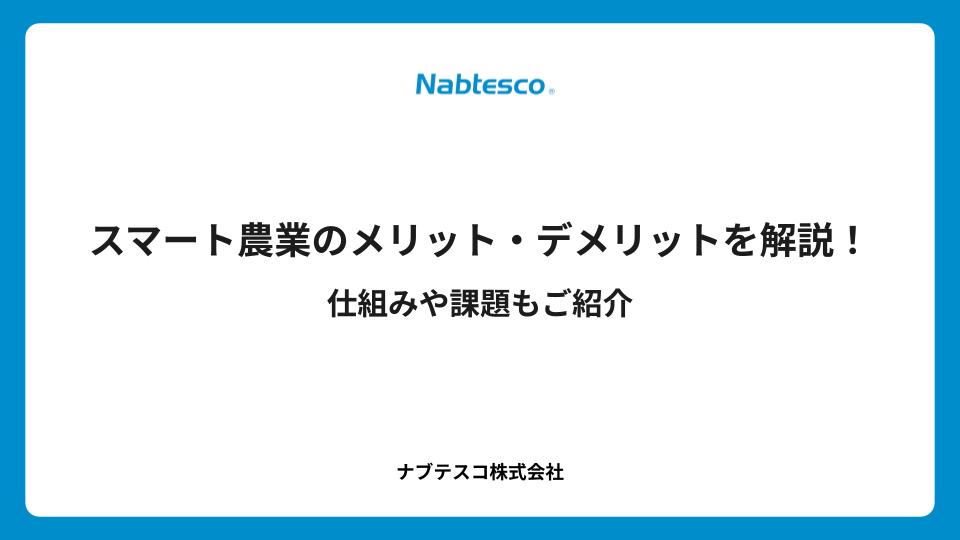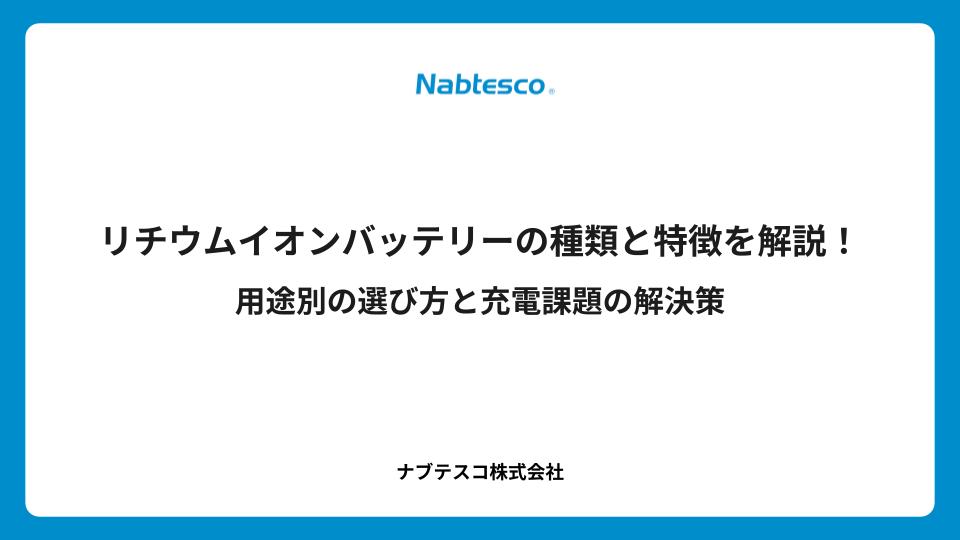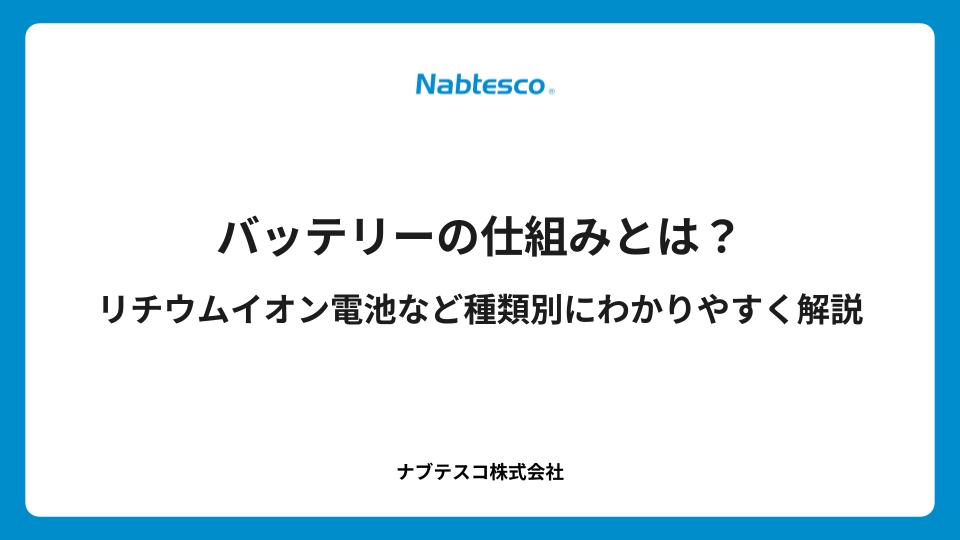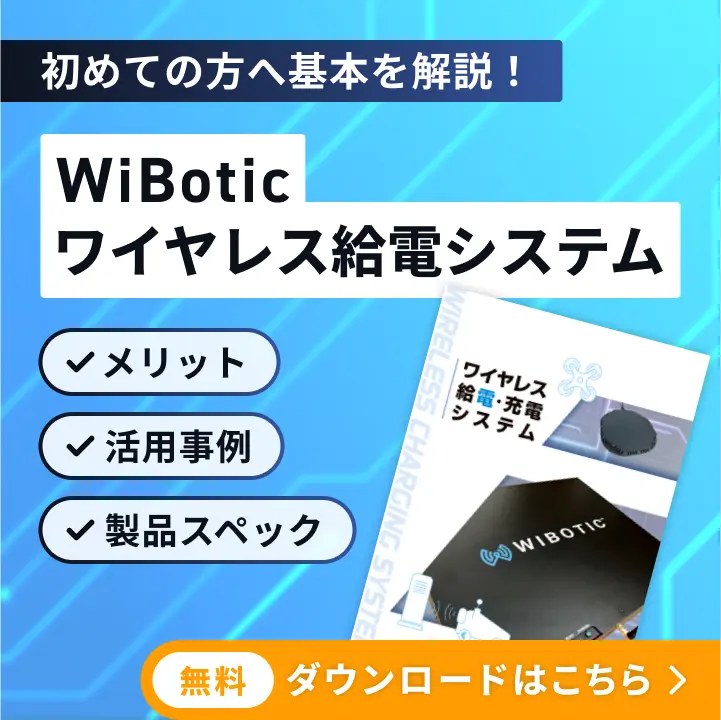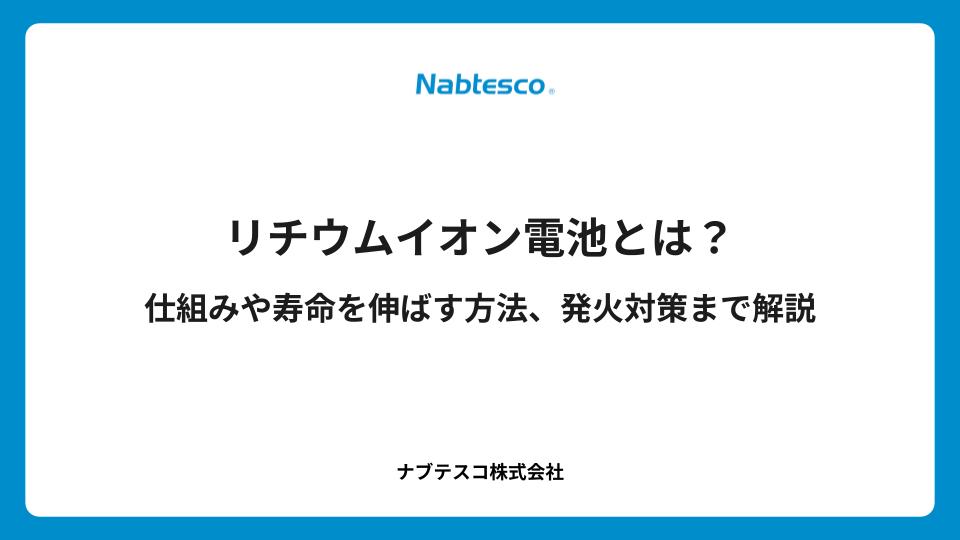
スマートフォンやノートパソコン、電気自動車など、現代の様々な電子機器に欠かせないリチウムイオン電池。製造業の現場でも、産業用ロボットや無人搬送車(AGV)、IoTデバイスなど、幅広い用途で活用されています。
しかし、リチウムイオン電池の基本的な仕組みや適切な取り扱い方法を理解していないと、性能劣化や安全リスクを招く可能性があります。
本記事では、製造業の経営層の方に向けて、リチウムイオン電池の基礎知識から寿命延長のコツ、安全対策まで詳しく解説します。さらに、充電の課題を解決する革新的なワイヤレス給電技術についてもご紹介いたします。
リチウムイオン電池とは?仕組みを解説
リチウムイオン電池は、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車(EV)から産業用ロボット、家庭用蓄電池に至るまで、現代社会のあらゆる場所で利用されている高性能な二次電池です。一度使い切ったら終わりではなく、繰り返し充電して使える点が大きな特徴です。
その高いエネルギー密度と長寿命により、私たちの生活や産業活動に不可欠な存在となっています。ここでは、リチウムイオン電池の基本的な構造、充電・放電の仕組み、そして他の二次電池との違いについて詳しく解説します。
リチウムイオン電池の基本構造
リチウムイオン電池は、主に以下の4つの主要な要素で構成されています。
正極(カソード): リチウムイオンを含む材料(例:コバルト酸リチウム、リン酸鉄リチウムなど)が使われ、電子を受け取る役割を担います。
負極(アノード): リチウムイオンを吸蔵・放出できる材料(主にグラファイトなどの炭素材料)が使われ、電子を供給する役割を担います。
電解液: リチウムイオンが正極と負極の間を移動するための媒体となる液体です。リチウム塩を有機溶媒に溶かしたものが一般的です。
セパレーター(分離膜): 正極と負極が直接接触してショートするのを防ぎつつ、リチウムイオンのみを通過させる微細な孔を持つ膜です。
これらの要素が層状に重ねられ、または巻かれて密閉された構造となっています。
充電・放電の仕組み
リチウムイオン電池の充電と放電は、リチウムイオンが正極と負極の間を行き来することで行われます。
充電時: 外部から電気エネルギーが供給されると、正極からリチウムイオンが電解液中を移動し、セパレーターを通過して負極に吸蔵されます。同時に、正極から放出された電子は外部回路を通って負極に移動します。この過程で電気エネルギーが化学エネルギーとして蓄えられます。
放電時: 機器を動かすために電池が使われると、負極に吸蔵されていたリチウムイオンが電解液中を移動し、セパレーターを通過して正極に戻ります。同時に、負極から放出された電子は外部回路を通って正極に移動し、この電子の流れが電流となって機器に供給されます。この過程で化学エネルギーが電気エネルギーに変換されます。
このように、リチウムイオンの移動と電子の流れが同期することで、エネルギーの充放電が行われます。
他の二次電池との違い
リチウムイオン電池は、他の二次電池(例:ニッケル水素電池、鉛蓄電池)と比較して、いくつかの顕著な優位性を持っています。
高エネルギー密度: 同じ体積や重量でより多くの電気エネルギーを蓄えることができます。これにより、小型・軽量化が求められるモバイル機器やEVでの採用が進んでいます。
高電圧: 一般的なセル電圧が3.6V〜3.7Vと高く、少ないセル数で高い電圧を得られます。
メモリー効果がない: 電池を完全に使い切る前に充電を繰り返しても、容量が低下する「メモリー効果」がほとんどありません。これにより、継ぎ足し充電が可能です。
自己放電が少ない: 使用していない時の自然放電が少なく、長期間保存しても容量が大きく減少しにくい特徴があります。
これらの特性により、リチウムイオン電池は現代のポータブル電子機器や電動モビリティの普及に大きく貢献しています。より詳細な情報は、経済産業省の資料なども参考にすると良いでしょう。
リチウムイオン電池の種類と特徴
リチウムイオン電池の種類
リチウムイオン電池は、主に正極活物質の種類によってその特性が大きく異なります。代表的な種類としては、LCO(コバルト酸リチウム)、NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム)、NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウム)、LFP(リン酸鉄リチウム)、LMO(マンガン酸リチウム)などが挙げられます。
LCO(コバルト酸リチウム)系
LCOは高いエネルギー密度が特徴で、スマートフォンやノートPCなどの小型電子機器に広く利用されてきました。しかし、コバルト資源の希少性やコスト、熱安定性の課題から、より安全で安価な代替品への移行が進んでいます。
NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム)系
NMCは、ニッケルの比率を高めることで高エネルギー密度と出力を両立させ、さらにマンガンとコバルトで安定性を向上させたバランスの取れたタイプです。電気自動車(EV)や電動工具、ポータブル電源など、幅広い用途で採用されています。
NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウム)系
NCAは、NMCと同様に高エネルギー密度と高出力を特徴とし、特にEVにおいて高性能を求める用途で採用されています。アルミニウムを加えることで安定性を高めていますが、ニッケルの比率が高いため熱安定性には注意が必要です。
LFP(リン酸鉄リチウム)系
LFPは、他のリチウムイオン電池と比較してエネルギー密度はやや低いものの、優れた安全性、長寿命、そして低コストが最大の強みです。熱暴走のリスクが低く、サイクル寿命が長いため、定置型蓄電池やバス・トラックなどの商用EV、産業用機器での利用が拡大しています。
LMO(マンガン酸リチウム)系
LMOは、マンガンを主成分とすることで、高い安全性と優れた出力特性を持ちます。比較的安価ですが、エネルギー密度とサイクル寿命は他の種類に劣る傾向があります。電動工具や医療機器など、高い瞬間出力を必要とする用途で利用されることがあります。
用途別の選び方
リチウムイオン電池を選定する際には、用途に応じて重視する性能や特性を明確にすることが重要です。安全性、エネルギー密度、出力特性、寿命、コストといった要素を考慮して最適な種類を選択します。
高エネルギー密度・小型軽量を重視する場合
スマートフォン、ノートPC、ドローンなどの携帯型電子機器や小型モビリティには、LCO、NMC、NCAといった高エネルギー密度を持つリチウムイオン電池が適しています。限られたスペースで長時間稼働させるために、高いエネルギー密度が求められます。
高出力・安全性を重視する場合
電気自動車(EV)や電動工具、産業用ロボットなど、瞬間的に大きな電力が必要とされる用途では、高出力と安全性の両立が重要です。NMC、NCAは高出力かつエネルギー密度も高いためEVに多く採用され、LFPは特に高い安全性と長寿命が求められる商用EVや定置型蓄電池に適しています。
長寿命・低コスト・安全性を重視する場合
定置型蓄電池、非常用電源、産業用無人搬送車(AGV)など、長期間にわたる安定稼働とコスト効率が求められる用途では、LFPが優れた選択肢となります。高い安全性と長いサイクル寿命により、メンテナンスコストの削減にも貢献します。
製造業におけるリチウムイオン電池の活用事例
リチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度、長寿命、急速充電性能といった特性から、製造業におけるさまざまな分野で活用が進んでいます。従来の電源では実現が難しかった、フレキシブルな運用や省スペース化、高効率化に貢献しています。
産業用ロボット・自動化設備での利用
産業用ロボットや自動化設備において、リチウムイオン電池は高出力と小型・軽量化のニーズに応えます。特に、ケーブルレス化が求められる移動型ロボットや、協働ロボットの電源として採用が進んでいます。
これにより、作業スペースの自由度が向上し、設置場所の制約が緩和されるとともに、配線作業の簡素化やメンテナンスコストの削減にも寄与します。
無人搬送車(AGV)・自律移動ロボット
工場や倉庫内で資材や製品を運搬する無人搬送車(AGV)や、より高度な自律移動ロボット(AMR)の動力源として、リチウムイオン電池は不可欠な存在です。長時間の連続稼働を可能にする高いエネルギー密度と、短時間での充電が可能な急速充電性能が、稼働率の向上と生産性維持に貢献します。
従来の鉛蓄電池と比較して、小型・軽量であるため、車両の設計自由度が高まり、積載量の増加にも繋がります。
IoTセンサー・モニタリングシステム
製造現場におけるIoT(Internet of Things)センサーやモニタリングシステムでは、広範囲にわたる機器のデータを収集するために、電源供給が課題となることがあります。リチウムイオン電池は、小型でありながら長期間の電力供給が可能なため、配線が困難な場所や移動体のセンサー電源として最適です。
設備の稼働状況監視、環境モニタリング、予知保全システムなど、多岐にわたる用途で活用され、製造プロセスの最適化とダウンタイムの削減に貢献します。
非常用電源・UPS(無停電電源装置)
データセンターや生産ライン、医療機器など、電力供給の途絶が許されない重要な設備において、リチウムイオン電池は非常用電源やUPS(無停電電源装置)として導入が進んでいます。瞬時に電力を供給する応答性の高さ、長寿命、そして鉛蓄電池と比較して大幅な小型・軽量化が実現できる点が大きなメリットです。
これにより、設置スペースの有効活用が可能となり、メンテナンス頻度の低減にも繋がるため、システム全体の信頼性と運用効率が向上します。
リチウムイオン電池の寿命を左右する要因
リチウムイオン電池の性能は、使用期間とともに徐々に低下します。この性能低下、すなわち寿命の短縮は、単一の要因だけでなく、複数の要素が複雑に絡み合って引き起こされます。電池の内部構造や化学反応に影響を与えるこれらの要因を理解することは、より長く安全に電池を使用するために不可欠です。
充放電サイクル数の影響
リチウムイオン電池の寿命を示す重要な指標の一つに「サイクル寿命」があります。これは、電池が所定の容量を維持しながら充放電を繰り返せる回数を指します。充放電を繰り返すたびに、電池内部の電極材料は膨張・収縮を繰り返し、構造が徐々に劣化します。
特に、負極の表面に形成されるSEI(固体電解質界面)層は、サイクルが進むにつれて厚くなったり、破壊と再形成を繰り返したりすることで、リチウムイオンの移動を阻害し、内部抵抗を増加させます。これにより、最終的に電池の蓄電容量が低下し、寿命が短くなります。
温度環境による劣化
リチウムイオン電池は、使用および保管される温度環境によってその寿命が大きく左右されます。
高温環境による劣化
高温環境は、リチウムイオン電池にとって最も有害な要因の一つです。高温下では、電解液の分解反応が加速され、ガス発生や電極材料の変質を引き起こします。
特に、正極材料の劣化が進行しやすく、リチウムイオンの貯蔵能力が低下します。また、内部抵抗が増加し、自己放電も促進されるため、容量低下が急速に進みます。極端な高温は、電池の安全性を脅かす熱暴走のリスクも高めます。
低温環境による劣化
低温環境自体は高温ほど急速な劣化を引き起こしませんが、低温下での充電は電池にダメージを与える可能性があります。低温で充電すると、リチウムイオンが負極にスムーズに挿入されにくくなり、負極表面に金属リチウムが析出することがあります。このリチウム析出は、電池の容量低下だけでなく、内部短絡や発火のリスクを高める原因となります。
保存状態と自然放電
リチウムイオン電池は、使用していなくても時間の経過とともに自然に放電します。これを自己放電(自然放電)と呼びます。自己放電によって電池残量が減少するだけでなく、完全に放電された状態(過放電状態)で長期間放置すると、電池に不可逆的なダメージを与えます。
特に、負極の銅箔が溶出したり、電極材料が劣化したりすることで、再充電できなくなったり、充電を受け付けにくくなったりします。適切な充電状態で保管することが、電池の寿命を保つ上で重要です。
過充電・過放電
リチウムイオン電池の寿命を短縮させるだけでなく、安全上のリスクも高めるのが過充電と過放電です。
過充電
過充電とは、電池が満充電状態に達した後も、さらに充電を続けることです。過充電は、正極材料の構造を破壊し、電解液の分解を促進します。これにより、ガスが発生したり、内部抵抗が増加したりして、容量が低下します。
さらに、過充電によって電池内部の温度が異常に上昇し、熱暴走や発火、爆発といった重大な事故につながる可能性が高まります。このため、多くのリチウムイオン電池には、過充電を防ぐための保護回路が内蔵されています。
過放電
過放電とは、電池が許容される最低電圧を下回るまで放電されることです。過放電状態になると、負極の銅箔が溶出したり、電極材料の結晶構造が不可逆的に変化したりします。特に、完全に放電された状態で長期間放置すると、電池が損傷し、再充電しても元の容量まで回復しなくなったり、全く充電できなくなったりすることがあります。
過放電は、電池の寿命を著しく短縮させるだけでなく、再充電時に内部短絡のリスクを高めることもあります。
リチウムイオン電池の寿命を伸ばす5つの方法
適切な充電管理(50-80%の範囲で使用)
リチウムイオン電池の寿命を延ばすには、満充電に近い状態や完全放電に近い状態を避ける充電管理が重要です。一般的に、バッテリー容量の50%から80%の範囲で使用することが推奨されています。
これは、フル充電や完全放電がバッテリーに大きなストレスを与え、内部抵抗の増加や電極の劣化を早めるためです。
継ぎ足し充電はリチウムイオン電池の特性上問題なく、むしろバッテリーへの負担を軽減し、サイクル寿命を延ばす効果が期待できます。過充電や過放電を避けることで、電池の化学的安定性を保ち、長期的な性能維持に繋がります。
温度管理の徹底(20-25℃の維持)
リチウムイオン電池は温度に非常に敏感です。特に高温環境下での使用や保管は、バッテリーの劣化を著しく加速させます。理想的な動作温度範囲は20℃から25℃とされており、この範囲を維持することが寿命を延ばす上で極めて重要です。
直射日光の当たる場所や、夏場の車内など、高温になる場所での放置は避けてください。また、極端な低温環境も性能低下や劣化の原因となることがあります。使用しないときは、涼しく乾燥した場所に保管し、バッテリーが過度に熱を持たないよう注意しましょう。
専用充電器の使用
リチウムイオン電池を充電する際は、必ずメーカーが指定する専用の充電器を使用してください。専用充電器は、バッテリーの電圧や電流特性に合わせて設計されており、過充電や過電流を防ぐための安全回路が内蔵されています。
非純正品や安価な充電器の中には、適切な充電制御が行われず、過電圧や過電流によってバッテリーが損傷したり、最悪の場合、発熱や発火の原因となるリスクがあります。PSEマークなどの安全認証が表示された製品を選び、安全性を確保することが不可欠です。
定期的なメンテナンス
リチウムイオン電池の寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスも欠かせません。具体的には、バッテリーの外観に膨張や破損がないかを確認し、充電端子に汚れや腐食がないかをチェックすることが含まれます。
また、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載している機器の場合、ファームウェアのアップデートが提供されることがあります。これにより、バッテリーの充電制御が最適化され、寿命の延長に貢献する可能性があります。長期間使用しない場合は、適切な充電状態(一般的には50%程度)で保管し、数ヶ月に一度は充電状態を確認することをお勧めします。
リチウムイオン電池の発火・爆発リスクと対策
リチウムイオン電池は高いエネルギー密度を持つ一方で、不適切な使用や製造上の問題により、発火や爆発のリリスクを伴うことがあります。ここでは、そのメカニズムと具体的な対策について解説します。
熱暴走(サーマルランアウェイ)のメカニズム
リチウムイオン電池の発火・爆発の根源的な原因は「熱暴走(サーマルランアウェイ)」と呼ばれる現象です。これは、電池内部で異常な発熱が一度発生すると、その熱がさらに化学反応を加速させ、自己発熱が連鎖的に進行して温度が制御不能な状態まで急上昇する現象を指します。
熱暴走の引き金となるのは、主に以下の要因です。
内部短絡: 電池内部の正極と負極を隔てるセパレーターが破損し、直接接触することで大電流が流れ、急激な発熱を引き起こします。
過充電: 過剰な充電により正極からリチウムイオンが過度に引き抜かれ、負極表面に金属リチウムが析出します。この析出した金属リチウムがデンドライト(樹枝状結晶)を形成し、セパレーターを突き破って内部短絡を引き起こすことがあります。
外部からの衝撃や変形: 落下や圧迫などにより電池構造が物理的に損傷し、内部短絡を誘発する可能性があります。
高温環境: 高温下での使用や保管は、電池内部の化学反応を促進させ、熱暴走のリスクを高めます。
一度熱暴走が始まると、電解液の分解や正極・負極材料の反応がさらに加速し、最終的には発火や爆発に至ることがあります。
発火の主な原因
リチウムイオン電池の発火・爆発は、熱暴走に至る様々な要因によって引き起こされます。主な原因は以下の通りです。
過充電・過放電: 充電しすぎると内部短絡のリスクが高まり、放電しすぎると電極構造が不安定になり、再充電時に危険性が増します。
外部からの衝撃・破損: 落下、圧迫、釘刺しなどにより電池内部が損傷し、セパレーターが破れて短絡する可能性があります。
高温環境での使用・保管: 直射日光下や高温になる車内などでの使用・保管は、電池の劣化を早め、内部圧力を上昇させ、熱暴走を引き起こしやすくなります。
製造不良・粗悪品: 内部に異物が混入していたり、セパレーターの品質が不十分だったりする粗悪品は、初期段階から内部短絡のリスクを抱えています。
不適切な充電器の使用: 電池の仕様に合わない電圧や電流の充電器を使用すると、過充電や過電流が発生し、発熱や損傷の原因となります。
異物混入: 電池製造時に微細な金属片などが混入すると、それがセパレーターを貫通し、内部短絡を引き起こすことがあります。
リチウムイオン電池の充電課題を解決するワイヤレス給電
リチウムイオン電池の充電時における安全性をさらに高める技術として、ワイヤレス給電(非接触充電)が注目されています。ワイヤレス給電は、ケーブルを接続する必要がないため、従来の充電方法が抱えるいくつかのリスクを低減できます。
接触不良による発熱リスクの低減: ケーブルの抜き差しや端子部の劣化による接触不良は、発熱や短絡の原因となることがありますが、ワイヤレス給電ではこのリスクがありません。
ケーブル損傷による短絡・感電リスクの排除: ケーブルの断線や被覆の損傷は、短絡や感電のリスクを伴いますが、ワイヤレス給電ではケーブル自体が不要なため、これらのリスクを排除できます。
密閉環境での充電: 防塵・防水性能を維持したまま充電が可能となり、水濡れや異物混入による故障・発火のリスクを低減できます。これにより、屋外や特殊な環境下での安全性向上に貢献します。
ワイヤレス給電は、利便性だけでなく、充電時の安全性を高める新たなソリューションとして、産業機器やロボット、医療機器など、幅広い分野での活用が期待されています。
まとめ
リチウムイオン電池は、現代の産業を支える不可欠なエネルギー源です。その高性能を安全に、そして長く使い続けるためには、適切な知識に基づいた運用が欠かせません。本記事では、リチウムイオン電池の仕組みから、寿命を延ばすための管理方法、そして発火リスクへの対策までを解説しました。
特に製造現場で活躍するAGVやロボットにとって、バッテリーの劣化は稼働率の低下やメンテナンスコストの増加に直結する大きな課題です。こうした課題を根本から解決する手段として、ワイヤレス給電システムは非常に有効です。
ナブテスコ株式会社が提供する「Nabtesco WiBoticワイヤレス給電・充電システム」は、この課題を解決する革新的なソリューションです。ケーブルを介した物理的な接続が不要なため、接触不良による発熱やケーブル損傷といった安全リスクを排除します。
さらに、充電のたびに機器を停止させる必要がなく、作業の合間に自動で充電を行う「機会充電」が可能になります。これにより、バッテリーへの負担が軽減され、寿命が大幅に延長されるだけでなく、設備の稼働率が向上し、生産性の最大化にも貢献します。
リチウムイオン電池の安全性向上と長寿命化、そして現場の生産性向上を実現する「Nabtesco WiBoticワイヤレス給電・充電システム」。より詳しい情報や導入に関するご相談は、ぜひナブテスコ株式会社にお問い合わせください。
ナブテスコのワイヤレス給電についてはこちら
https://wireless-power.nabtesco.com/